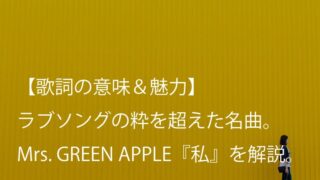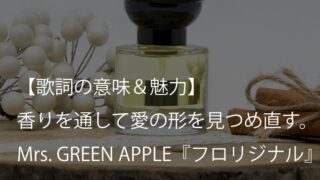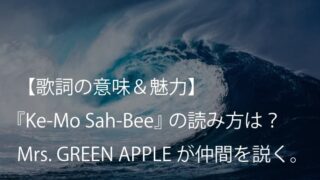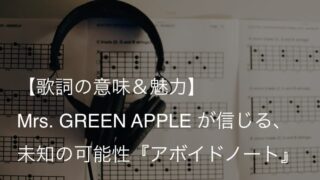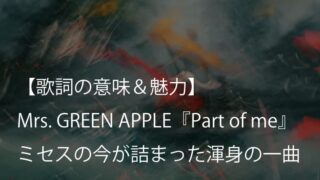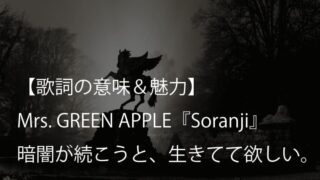Mrs. GREEN APPLE(ミセス)『リスキーゲーム』の歌詞とその意味について考察していきます。
“人生はリスキーゲーム”という一見危ういフレーズから始まるこの曲は、日々を”その日暮らし”で生きるリアルな感情を、切なさと軽やかさで包み込みます。
みなさんの”リスキーな毎日”にそっと寄り添ってくれるような一曲です。
本記事では、歌詞に込められたメッセージをフレーズごとに丁寧に読み解き、楽曲全体を通じて伝わる深い意味を探っていくので、ぜひ最後までご覧ください!
あくまで筆者自身が解釈したものになるので、一つの参考として受け取っていただけると幸いです。
今なら無料で音楽聴き放題!
\\いつでも解約OK!//
Mrs. GREEN APPLE『リスキーゲーム』歌詞
歌手:Mrs. GREEN APPLE
作詞:大森元貴
作曲:大森元貴
収録:ミニアルバム『Variety』
発売日:2015年7月8日(水)
人生はリスキーゲーム
寝転がりおかえり
勝ち負けではない
でもこだわるの
アイデアに負けそうなのね
ならね 着飾って
リスキーゲームで遊んでいようよ
もう散る命の輪でほらまた明日
嘘つきポーズで嘆いていようよ
目の前の明日って未来だけ
その日暮らしだから
この街はジオラマワールド
小人の寝返り
踊り疲れたんだ
眠りはしないよ
アイデアに勝ちそうなのね
でもね 勝てないよ
ハッピーエンド自慢はもういいよ
所詮また不幸の風吹いて
ほらまた戻る
怒りのポーズで踊ってみようよ
目の前の愛するべき未来だって
その日暮らし
ひとは誰しもあれこれいいなと
他人の持つモノを羨ましく思う
このペースで生きていて
どのケースで死んでって
その間に思う幾つもの感情と
寄り添って歩いてって
その結果がなんだって
歩いた足あと数えればいいだろうリスキーゲームで
『リスキーゲーム』歌詞の意味&楽曲背景
この曲『リスキーゲーム』は、人生を勝ち負けで測らずに楽しむというテーマを土台にしつつ、その本質は「刹那的な日常」を鮮やかに切り取った作品です。
日々変わる感情、他人との比較、理想と現実の間で揺れる心。それらを、大森くんらしい遊び心と鋭い観察眼で描き出します。
象徴的なのは「その日暮らし」という言葉。予定調和や正解を求めるのではなく、今この瞬間を生きることの美しさと危うさをあわせ持ったメッセージが込められています。
軽やかなメロディの中に潜む毒と救いが、聴く人の胸に深く刻まれる一曲です。
公式音源の紹介
公開されている公式音源がこちら。
ここからはフレーズごとに歌詞考察をしていきます。
1番:歌詞の意味
まずは1番Aメロの歌詞。
人生はリスキーゲーム
寝転がりおかえり
勝ち負けではない
でもこだわるの
「人生はリスキーゲーム」という冒頭は、価値観の宣言であり、同時に”人生の見方”の提示。大森くんは、人生を勝ち負けで測らないと宣言しますが、すぐに「でもこだわるの」と続けます。この一言で、完全な達観や諦めには立たない姿勢が見えます。
つまり「スコアで勝負しないが、プレイの美学は守る」というスタンスです。このねじれが、曲全体の推進力になっているように感じます。
「勝ち負けではない」と言った直後に”こだわり”を残すのは、欲や矜持を肯定する行為です。ここでいう”こだわり”は、結果への執着ではなく「自分のやり方」への信念ではないでしょうか。勝敗のゲームから降りるのではなく、自分だけのルールを課して生きる態度です。それゆえに”リスキー”でもあります。正解とされる枠組みに乗らないことは、孤独や批判にさらされるリスクを伴うから。
さらに、このAメロは後半に登場する「その日暮らし」を先取りする役割も担っていそうです。勝ち負けを脇に置きつつも”こだわる”ということは、評価が遅れてやってくるか、あるいは来ないかもしれないということ。だからこそ、「今日をどうプレイするか」に焦点が合うのではないでしょうか。
Aメロは軽やかに、”生き方のOSを更新する”ことを宣言しているのだと思います。
続く1番Bメロの歌詞。
アイデアに負けそうなのね
ならね 着飾って
「アイデアに負けそうなのね」という一言は、抽象的な”アイデア”を擬人化し、その攻勢に押される自分を描いています。
ここでの”負けそう”は、他者の創意や時代の流行、アルゴリズムが生み出す”正しさ”に飲み込まれそうな不安を映し出しているのではないでしょうか。その中には、クリエイターとしての実感と、生活者としての焦燥感が同時に息づいているようにも感じます。
続く「ならね 着飾って」は秀逸で、中身を即座に作り替えるのではなく、まず”見た目=態度”から整えるという発想です。これは単なる虚飾ではなく、プレイに臨むためのコスチュームのようなものだと思います。
舞台に上がる前に衣装を纏うように、心の姿勢を”装う”ことで、押し寄せる外圧と対等に渡り合う準備をする。大森くんの言葉には、自己欺瞞ではなく”演出の自覚”が漂っています。演じることは偽ることではなく、自分の核を守るためのラッピングとして機能しているのではないでしょうか。
そして1番サビの歌詞。
リスキーゲームで遊んでいようよ
もう散る命の輪でほらまた明日
嘘つきポーズで嘆いていようよ
目の前の明日って未来だけ
その日暮らしだから
「リスキーゲームで遊んでいようよ」という呼びかけは、世界の厳しさをそのまま受け止めるのではなく、”遊び”という枠で包み込む発想です。ここでの遊びは軽率さではなく、ルールや役割、試行錯誤を含み、失敗を学びに変える装置。つまり、しなやかに戦うための方法だと思います。
「もう散る命の輪」というフレーズは、有限な時間を円環として描きます。輪は回り続ける一方で散っていく。循環と消耗が同時に進む矛盾の美しさが、今動く理由を立ち上げます。輪の中で立ち止まるより、その回転に身を投じて加速するほうを選ぶということだと感じました。
「嘘つきポーズで嘆いていようよ」という言葉も印象的です。嘆きは本物でも、あえて”ポーズ”として表現する。感情をむき出しにせず、ダンスのように動きへと変換する姿勢。これは感情を行動に翻訳し、同時に自分を壊さない距離を保つ方法なのではないでしょうか。
「目の前の明日って未来だけ/その日暮らしだから」という言葉は、遠い未来像を万能化せず、”明日”だけに焦点を絞ります。そうすることでコントロールできる可能性を高める。壮大なビジョンよりも、一日分の約束を積む。
この姿勢に、”勝ち負けではない”生き方の具体例が宿ります。
2番:歌詞の意味
2番Aメロの歌詞。
この街はジオラマワールド
小人の寝返り
踊り疲れたんだ
眠りはしないよ
「この街はジオラマワールド」の描写は、視点を一気に遠ざけ、街全体を”模型”として捉えます。まるでドローンから見下ろすように、縮尺を変えて眺めることで、自分の存在の小ささと、俯瞰する自由さが同時に得られます。
「小人の寝返り」という比喩は、個々の選択や感情の揺れを、模型の中での細やかな動きとして描くもので、「世界=箱庭」「自分=ピース」というメタ的な視点を与えています。
「踊り疲れたんだ/眠りはしないよ」という一見矛盾したフレーズは、現代的な疲労のあり方を的確に表しているように感じます。体は疲れているのに、神経が高ぶって眠れない。エネルギーは残りわずかでも、プレイを続ける義務感と高揚感が入り混じる。そんな状態ではないでしょうか。この対句は、やめられないSNSや止まらない思考のループを思わせます。
続く2番Bメロの歌詞。
アイデアに勝ちそうなのね
でもね 勝てないよ
「アイデアに勝ちそうなのね」という一瞬の昂揚は、創作や生活の”手応え”を掴んだ瞬間の高揚だと思います。しかし即座に「でもね 勝てないよ」と自己相対化が入る。ここに、大森くんの誠実さがよく表れているように感じました。
勝利は点であり、流れではありません。今日の勝利が明日も有効とは限らない。だからこそ、勝敗より”続け方”が問題になるのです。
このBメロは、1番Bメロの鏡像でもあり、往復運動そのものがこの曲の真理を語っているように思えます。負けそう→勝ちそう→でも勝てない。結論は出ない。けれど往復するたびに、プレイヤーとしての技量と体力は増す。ここで歌詞が教えてくれるのは、結論ではなく往復の効用なのだと思います。
そして2番サビの歌詞。
ハッピーエンド自慢はもういいよ
所詮また不幸の風吹いて
ほらまた戻る
怒りのポーズで踊ってみようよ
目の前の愛するべき未来だって
その日暮らし
「ハッピーエンド自慢はもういいよ」という一行は、他者との比較に疲れた現代の空気を鋭く断ち切ります。成果や成功を見せびらかすことが日常化すると、見る側は刺激を受けるどころか、自己評価をゆがめやすくなるということではないでしょうか。
歌詞はそれを”もういい”と切り離し、視線を自分の足元へと引き戻します。
続く「所詮また不幸の風吹いて ほらまた戻る」には、幸と不幸が行き来する可逆的な性質への理解が込められていそうです。追い風も向かい風も長くは続かない。ならば、風向きに振り回されるより、帆の張り方を覚える方が賢いという発想ではないでしょうか。
さらに「怒りのポーズで踊ってみようよ」は、怒りを破壊ではなく、動きや型に収めて出力するという提案だと思います。ネガティブな感情をダンスのように運動化し、エネルギーに変える、具体的で優しい指南のように感じました。
「目の前の愛するべき未来だって/その日暮らし」では、1番サビの”明日=未来だけ”という近未来限定の視点から、さらに”愛するべき”という倫理的な視座が加わっています。
未来を愛し、育てる対象として見る姿勢。ここに曲の成熟が表れ、単なる刹那の肯定から、関係性としての明日へと移行します。“その日暮らし”も、無計画の放棄ではなく、一日を丁寧に手入れする暮らし方として読み替えられそうです。
その後はCメロから大サビへと向かいます。
ひとは誰しもあれこれいいなと
他人の持つモノを羨ましく思う
このペースで生きていて
どのケースで死んでって
その間に思う幾つもの感情と
寄り添って歩いてって
その結果がなんだって
歩いた足あと数えればいいだろうリスキーゲームで
ここは、この曲の哲学の核心だと思います。
「ひとは誰しも…羨ましく思う」という一節で、人間全般に射程を広げ、比較する本能を否定せずに認めます。抑え込むのではなく、「そう思うよね」とまず受け入れる。ここが肝心なところだと感じました。自己嫌悪から始めないことで、認知 → 編集という順で進むための第一歩になるのではないでしょうか。
「このペースで生きていて/どのケースで死んでって」では、「ペース/ケース」という頭韻の軽やかさが、重いテーマ(生と死)をやわらかく通してくれます。言葉遊びの楽しさで重さを中和し、聴き手を身構えさせずに核心へと導いてくれるのです。
さらに「その間に思う幾つもの感情と/寄り添って歩いてって」では、価値の焦点がゴール(生/死)から”間”へと移り変わります。人生の主役は、終着点ではなく、その途中に生まれる感情群だという視座の反転ではないでしょうか。
そして”寄り添う”主体は自分自身です。湧き上がる感情に押し流されるのではなく、伴走者として並走する。これは自己受容を詩的に表現した一節なのだと思います。
最後の「その結果がなんだって/歩いた足あと数えればいいだろう」では、勝敗や達成の最終評価を宙づりにしています。その代わり、「足あと」という具体的で可視化できる指標を提示する。歩いた距離、選んだ路地、曲がった角、その積み重ねが”私”を証明するということ。成果の絶対値ではなく、痕跡の総量こそが生の証だという思想ではないでしょうか。
そしてラストで再び響く「リスキーゲームで…」は、もはや挑発ではなく合言葉なのかもしれません。Aメロで掲げられた宣言は、Bメロでの実践を経て、2番サビの倫理観(愛するべき未来)とCメロの尺度(足あと)に繋がり、ここで円環を閉じる。
序盤でただ散っていた”輪”は、終盤では意味を帯びた意志の輪に書き換えられます。
「明日もまたゲームは続くが、もう構えは知っている」。勝ち負けは脇に置き、こだわりを携え、怒りはポーズに、嘆きは踊りに変える。
ここで描かれるのは、生きるためのルーティンの確立なのだと思います。それは「歌い直し」として楽曲の中に定着し、終わりではなく「また始めよう」という地点に着地します。ポップでありながら、日々の実践に役立つ実用的な哲学の歌。それがこのラストです。
ぜひ歌詞の意味にも注目しながら、この曲『リスキーゲーム』を聴いてみて下さい!
その他ミセスのおすすめ曲
-320x180.jpg)
-320x180.jpg)
-320x180.jpg)
-320x180.jpg)
-320x180.jpg)
今なら無料で音楽聴き放題!
\\いつでも解約OK!//

.jpg)


-640x360.jpg)

-640x360.jpg)
-640x360.jpg)
-640x360.jpg)
-640x360.jpg)