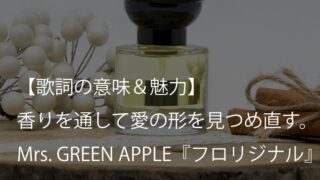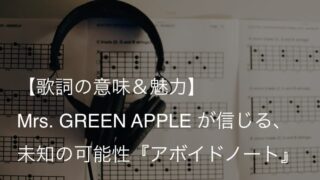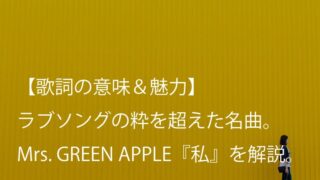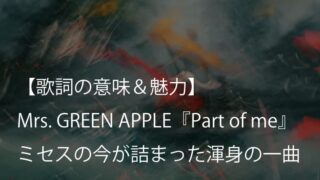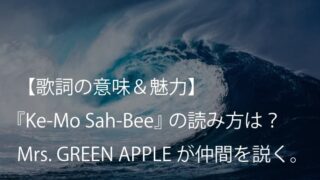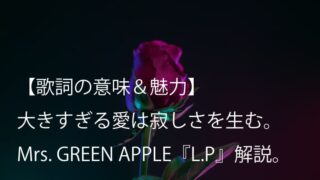Mrs. GREEN APPLE(ミセス)『夏の影』の歌詞とその意味について考察していきます。
この曲は、キリンビバレッジ『キリン 午後の紅茶』CMソングとして起用された一曲。
ゆっくりと、でも見えない速さで、あの夏の風がいまも頬を撫でる。
季節の”せい”にして自分を守ることも、相手を傷つけないための優しさだ。そんな穏やかな倫理が漂う、成熟のサマーソングです。
本記事では、歌詞に込められたメッセージをフレーズごとに丁寧に読み解き、楽曲全体を通じて伝わる深い意味を探っていくので、ぜひ最後までご覧ください!
あくまで筆者自身が解釈したものになるので、一つの参考として受け取っていただけると幸いです。
今なら無料で音楽聴き放題!
\\いつでも解約OK!//
Mrs. GREEN APPLE『夏の影』歌詞
歌手:Mrs. GREEN APPLE
作詞:大森元貴
作曲:大森元貴
収録:配信限定シングル『夏の影』
発売日:2025年8月11日(月)
吹いた
そよ風が
夏を揺らすの
伸びた
影が
限りを知らせるの
汗ばんだ
シャツで
未来を語るの
ゆっくりと
ゆっくりと
見えない速さで
進んでゆく
夏の暑さのせいにして
ただ 所為にして
火照った心を隠してる
夏の影のせいにして
また 所為にして
溶けた氷と時間を紡ぐの
吹いた
そよ風が
夏を揺らすの
日に焼けた
肌が
雲を動かすの
無垢な笑顔は
どこまで続いていけるの?
ゆっくりと
ゆっくりと
見えない速さで
大人になってゆく
夏の蝉のせいにして
ただ 所為にして
胸につかえた言葉は隠れる
夏の影のせいにして
また 所為にして
まだまだ溶けないで
コップの氷よ
過ごしていた
あの夏の思い出は
今でも瞼の裏で生きてる
恋をした
その夏に恋をしていた
あの風はどこかで
あなたに吹いていればいいなそうだといいな
『夏の影』歌詞の意味&楽曲背景
この曲『夏の影』は、夏という季節そのものを時間のものさしに見立て、恋と記憶の輪郭をそっとなぞる楽曲です。
繰り返される「〜のせいにして」という言い回しは、未熟さや照れを丸ごと肯定する装置として働き、火照りや蝉の鳴き声、長く伸びる影、解けていく氷などの手触り感のあるイメージが、過ぎゆく時間の不可逆性を優しく知らせます。
サビで季節のせいにして隠した言葉は、Cメロで「その夏に恋をしていた」という告白に変わり、最後は「あなたに吹いていればいいな」という風の願いで締めくくられる。
ミセスらしい表現で、懐かしさを今の形で感じさせてくれる、みずみずしい一曲です。
公式MVの紹介
YouTubeにて公開されている公式MVがこちら。
ここからはフレーズごとに歌詞考察をしていきます。
1番:歌詞の意味
1番Aメロの歌詞。
吹いた
そよ風が
夏を揺らすの
伸びた
影が
限りを知らせるの
「吹いた/そよ風が/夏を揺らすの」という冒頭では、本来「夏→風」となるはずの因果関係が逆転し、ほんの小さな風が季節全体を揺り動かすという、少し大げさな描写で始まります。
ここで注目すべきは「そよ風」の「そよ」というやわらかな響きです。強い風ではなく、かすかに肌をかすめるような優しい風。その”弱い力”が「夏を揺らす」という大きな変化を引き起こすことで、語り手の感受性がとても繊細になっている、つまり「恋の始まり」のような心の動きを表しているのではないでしょうか。
「伸びた/影が/限りを知らせるの」は、影の長さで時間の流れを感じ取るということだと思います。ここでの「限り」は二つの意味を持っているのではないでしょうか。
①一日の終わり(夕方が近づいている)
②夏という季節の終わり
このように、短い一瞬と長い時間の両方を重ねて見せているのだと思います。
また、「影」は「光が強ければ強いほど濃く長くなる」という矛盾を含んでおり、楽しい時間が濃くなるほど、終わりもはっきりと感じられるという、切なさを予感させる仕掛けになっている?ようにも感じました。
そして1番Aメロ後半部分。
汗ばんだ
シャツで
未来を語るの
「汗ばんだ/シャツで/未来を語るの」は、体の感覚(汗)と抽象的なもの(未来)がつながるユニークな表現。
シャツが肌に張りつくような感覚は不快に思えるかもしれませんが、その”密着感”が、逆に親密な関係を表しているように感じられました。
また、汗は「慣れない暑さ」の象徴でもあり、まだぎこちない関係のドキドキ感を表しているとも言えそうです。さらに、これまでの行がすべて「〜の」で終わっていることで、断定を避け、あくまで観察の視点で語っているような印象を与えます。
続く1番Bメロの歌詞。
ゆっくりと
ゆっくりと
見えない速さで
進んでゆく
このパートは、「時間の感じ方の不思議さ」をテーマにした一文ではないでしょうか。体感ではゆっくり進んでいるように思えるけれど、実際には目に見えないほど速く進んでいる。そんな矛盾が描かれています。
「速さ」を「見えない」と表現することで、聞く人の時間感覚を揺さぶり、このあとの歌詞全体を「時間」というテーマで読むきっかけを作ってくれているように感じました。
また、「ゆっくりと」という言葉を繰り返すことで、まるで深呼吸を促すように、聞く人の心拍やテンポを落ち着かせ、感情が高ぶるサビ部分への準備を整えてくれます。
そして「進んでゆく」の”ゆく”という表記は、少し古風な言い回しですが、その分、音の響きが柔らかくなり、時間がなめらかに流れていくような印象を与えます。
ここで特に大切なのは、”進んでゆく”の主語がはっきり書かれていない点ではないでしょうか。季節が進んでいるのか、それとも2人の関係が進んでいるのか。あるいはその両方かもしれません。あえて主語をぼかすことで、聴く人自身が自分の体験を重ねやすい、想像の余地を生んでくれているのだと思います。
そして1番サビの歌詞。
夏の暑さのせいにして
ただ 所為にして
火照った心を隠してる
夏の影のせいにして
また 所為にして
溶けた氷と時間を紡ぐの
「夏の暑さのせいにして/ただ 所為にして」の”せい”という言葉を、あえて漢字で「所為」と書くことで、少しだけ重たいニュアンスが加わります。
口では軽く”夏のせいだよ”と冗談のように言っていても、どこかで本当は自分の気持ちを自覚していて、ちょっとした”照れ”や”気まずさ”を感じている。そんな複雑な心の内が、漢字表記にじんわりとにじみ出ているように感じました。
「火照った心を隠してる」は、暑さによる体の火照り(外的な原因)と、恋による心の火照り(内的な原因)を重ねた表現だと思います。
暑さのせいにしておけば、本当の気持ちは隠したままでいられる。つまりこれは、臆病というよりも、大切な関係を壊さないための”思いやりある擬態”なのではないでしょうか。そしてこの”隠す”という行動は、後に出てくる「紡ぐ(つむぐ)」という言葉にもつながっていきます。
「夏の影のせいにして/また 所為にして」の”また”は、単なる繰り返しではありません。“何かうまく言えないときは、季節のせいにすればいい”という、ある種の”心の逃げ道”ができあがっているということではないでしょうか。これは、思春期特有の、傷つかないための自己防衛でもあり、とてもリアルな感情だなと感じました。
そして最も印象的なのが「溶けた氷と時間を紡ぐの」という一行。氷は、時間の流れを”目に見える形”にしてくれる存在です。
氷がグラスの中で「チリン」と鳴る音は、会話が途切れた瞬間をさりげなく埋めてくれる。グラスの表面に水滴が増える様子は、時間が少しずつ進んでいる証。そして、氷が溶けていく過程は、”温度が均(なら)される”ことの象徴であり、つまり2人の心の温度差が少しずつ近づいていくことを意味しそうです。
ここでの「紡ぐ」は、単に言葉を交わすことだけでなく、沈黙さえも関係の一部として丁寧に編み込んでいくような、やさしいまなざしを感じさせます。
サビでは、何でも夏のせいにしてしまうことを、無責任なこととは描いていません。むしろそれを、相手との距離を壊さないための”やわらかなクッション”として肯定的に捉えているのだと思います。
2番:歌詞の意味
2番Aメロの歌詞。
吹いた
そよ風が
夏を揺らすの
日に焼けた
肌が
雲を動かすの
無垢な笑顔は
どこまで続いていけるの?
「日に焼けた/肌が/雲を動かすの」は、ちょっと大げさだけれど、その誇張が気持ちいいフレーズ。日焼けした肌、つまり”自分の熱”が空の景色にまで影響しているように感じられる。そんな錯覚をあえて言葉にしてくれているのだと思います。
これは、自分の感情や体の変化が、世界そのものに影響しているように思える、青春特有の何でもできそうな気分をうまく表現しているのではないのでしょうか。
さらに、”雲”という存在もポイントです。地上から見ると雲はゆっくり動いているように見えますが、実際は高い空で強い風に流されていて、かなり速く動いています。この「見た目の遅さ/実際の速さ」という構造は、1番の「ゆっくりと/見えない速さで」とのつながりもあり、この曲全体の時間の不思議さを感じさせる伏線にもなっています。
そして「無垢な笑顔は/どこまで続いていけるの?」というフレーズは、この曲の中で唯一、はっきりと”問い”として投げかけられている部分です。ここで言う「無垢」とは、子どもっぽさや未熟さのことではなく、損得や計算抜きの、純粋な反応や感情を指しているような気がしました。
この問いは、相手に向けられているようでありながら、自分たち自身に向けられてもいるのではないでしょうか。笑顔は自然に続いていくものなのか?それとも、意識して続けようとしているのか?この問いによって、曲のはじめからじわじわと感じていた”終わりの気配”を、ここでついにハッキリと意識させられます…。
そして特に注目すべきなのは、「続いていけるの?」という表現の仕方です。「続くの?」と聞くのではなく、「続いていけるの?」という言い回しにしたことで、「その状態を続けていこうとする努力や選択の余地」も含まれているのだと感じました。
続く2番Bメロの歌詞。
ゆっくりと
ゆっくりと
見えない速さで
大人になってゆく
このパートは、1番Bメロのフレーズを繰り返しながら、そこに「大人になる」という言葉を加えることで、時間の流れという抽象的なイメージが、成長という具体的な変化に置き換えられています。
ここでも語尾は「〜ゆく」が使われていて、音の響きにやわらかさがあり、「大人になる」という変化をどこか受け入れているような、静かな成熟の気配を感じさせます。
つまり、成長そのものは時間とともに自然に起きてしまうけれど、「無垢でいようとするかどうか」は、その人の態度や心がけにかかっている。2番では、そんな静かな倫理観をやさしく差し出しているのではないでしょうか。
そして2番サビの歌詞。
夏の蝉のせいにして
ただ 所為にして
胸につかえた言葉は隠れる
夏の影のせいにして
また 所為にして
まだまだ溶けないで
コップの氷よ
1番では”暑さ”という外気のせいにして自分の気持ちを隠していましたが、2番では”音”の風景、つまり蝉の声が前面に出てきます。「夏の蝉のせいにして」は、蝉の鳴き声がうるさいから自分の声が届かない、言ってもかき消される、という言い訳を成立させています。
蝉の大合唱は、自然の中に満ちる圧倒的な外の音であり、自分の心の音をかき消してしまう背景音です。つまり、「言えない理由」が自然の中にある、というふうに描かれています。
「胸につかえた言葉は隠れる」では、言葉が自分の意思で勝手に隠れてしまうように描かれています。ここでの言葉は、話し手の「道具」ではなく、自分の意思を持った存在として扱われているのではないでしょうか。
これは、自分の気持ちをうまく伝えられないことを「臆病さ」や「弱さ」ではなく、自然なこととして受け止める、やさしい視点を表しているようにも感じました。
そして極めつけが「まだまだ溶けないで/コップの氷よ」というフレーズ。1番では、氷は”対話を紡ぐ時間のしるし”として使われていましたが、ここでは”時間を止めるもの=時間のブレーキ”として描かれています。
実際の氷も、表面積が小さいほど溶けにくく、グラスの中の温度と外気の温度が近づくと溶ける速度が遅くなります。そうした物理的な性質を踏まえて、ここでは「この時間が終わってほしくない」という祈りの気持ちが込められているのではないでしょうか。
その後Cメロ・大サビと歌詞が続きます。
過ごしていた
あの夏の思い出は
今でも瞼の裏で生きてる
恋をした
その夏に恋をしていた
このCメロでは、それまでと比べて時間の流れが大きく変わります。
「過ごしていた/あの夏の思い出は/今でも瞼の裏で生きてる」というフレーズでは、過去に体験していたことが、ただの思い出として残っているのではなく、今も生きていると表現されています。
ここでの記憶は、単なる記録ではなく、自分の内面で今も動き続けている”いのち”のような存在です。つまり、過去は過ぎ去ったものではなく、現在の自分を静かに、でも確かに支えている。そのようなあたたかく、やさしい時間の感覚が伝わってきます。
そして、とても繊細なのが「恋をした/その夏に恋をしていた」というフレーズです。直前では「あの夏」と言っていたのに、ここで急に「その夏」に変わっています。この指示詞(あの/その/この)の使い分けには、日本語ならではの心理的な距離感が表れています。
「あの夏」は、少し離れたところから見るような、客観的な視点。「その夏」は、相手と一緒に思い出しているような、共有された記憶の感覚。
つまり語り手は、自分とあなたが同じ夏を共有していたと感じているわけです。
さらにこの文は、「恋をした(=あなたに対して)」と、「その夏に恋をしていた(=季節そのものへの愛)」という2つの恋が重なっています。
誰かへの恋と、あの時間全体への恋。これは、ただ過去を振り返っているのではなく、「思い出している今」という時間にも、愛情が向けられているということかもしれません。
ここでは、それまで「言わずに」きた想いを、今度は言葉の濃度で丁寧に包み直していくパートです。過去と現在をつなぐ橋のような役割を果たし、このあとに来るラストの祈りのパートへと、説得力のある流れをつくっています。
あの風はどこかで
あなたに吹いていればいいなそうだといいな
「あの風はどこかで/あなたに吹いていればいいな」のフレーズは、これまで続いてきた”私たち”という関係から”あなた”個人へと視点が移る、重要な場面です。ここでは、風を「自分たちのもの」として独占しようとはしていません。
どこか遠くで、今のあなたにも風が吹いていればいいなと願うことで、相手の今をそっと尊重する。成熟した愛のかたちが表れています。
風は目に見えず、形を持たず、誰のものにもなりきれません。だからこそ、同じ風をどこかで感じているかもしれない、という偶然のつながりに期待を託しているのかもしれません。
そして最後の「そうだといいな」には、願いを押しつけることのない、やわらかな終わり方が込められています。ここでは、”そうであってほしい”という気持ちはあるけれど、それを確認しようとはしない。「確かめない」ことで相手の自由を守ろうとする、優しい倫理が成立していると言えます。
これは別れや冷たさではありません。むしろ、「思い出を壊さずにそのまま残したい」という気持ちから、あえて距離を取るという繊細なふるまいではないでしょうか。
まさにタイトルの「夏の影」が示すように、影は光に寄り添ってはいるけれど、光そのものではありません。つまり、”近づきすぎると壊れてしまうようなもの”を、大切に見守るという態度が貫かれているのだと思います。
構成面でも、ここまで何度も繰り返されてきた「〜のせいにして」というフレーズが、最後には出てこなくなります。その代わりに登場するのが、”風”という存在への委ね。
これにより、「責任転嫁」や「気持ちのごまかし」として使ってきた言葉たちが、相手の自由を認めるやさしさへと、静かに昇華しています。
つまり、この曲は、最初は「自分を守るための言い訳」から始まり、最後には「相手を縛らないための愛」へと変わっていく。その過程自体が、ささやかで美しい変化=”静かな革命”として描かれているのではないでしょうか。
ぜひ歌詞の意味にも注目しながら、この曲『夏の影』を聴いてみて下さい!
その他ミセスのおすすめ曲
-320x180.jpg)
-320x180.jpg)
-320x180.jpg)
-320x180.jpg)
-320x180.jpg)
今なら無料で音楽聴き放題!
\\いつでも解約OK!//

.jpg)



-640x360.jpg)
-640x360.jpg)
-640x360.jpg)
-640x360.jpg)
-640x360.jpg)
-640x360.jpg)