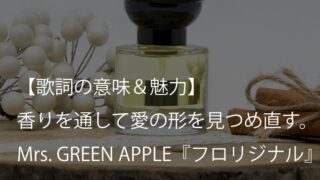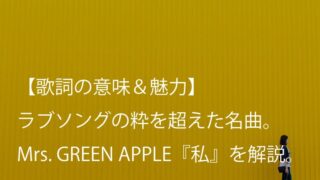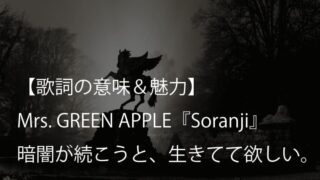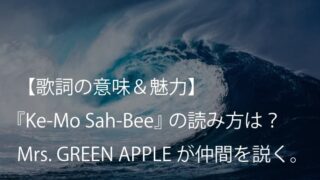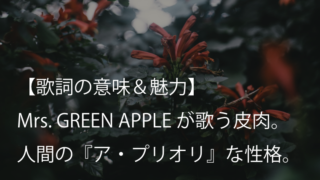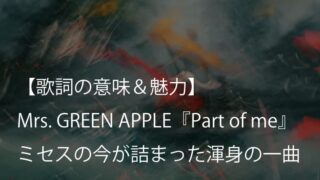Mrs. GREEN APPLE(ミセス)『橙』の歌詞とその意味について考察していきます。
この曲は、5thフルアルバム『ANTENNA』の10曲目に収録された楽曲。
旭化成不動産レジデンス『ATLAS』のブランドCMソングとしても起用されました。
夕焼け色の橙(だいだい)は、痛みも、歓びも、どちらも包み込んでくれる色です。
どんなに街が変わっていっても、私たちの中にある「変わらないもの」は、たしかに残っている。そんな確信を、懐かしさだけで終わらせず、やさしい現在形の言葉にして、私たちに届けてくれる曲になります。
本記事では、歌詞に込められたメッセージをフレーズごとに丁寧に読み解き、楽曲全体を通じて伝わる深い意味を探っていくので、ぜひ最後までご覧ください!
あくまで筆者自身が解釈したものになるので、一つの参考として受け取っていただけると幸いです。
今なら無料で音楽聴き放題!
\\いつでも解約OK!//
Mrs. GREEN APPLE『橙』歌詞
歌手:Mrs. GREEN APPLE
作詞:大森元貴
作曲:大森元貴
収録:5thフルアルバム『ANTENNA』
発売日:2023年7月5日(水)
学んだ日々を思い出すでしょう
幼き日に見た夕焼け空を
懐かしいねと語り合えば
現実に愛のある毛布が掛かる
いつだって僕らはあの日のままだ
いつだって僕らはあの日のままだ
帰りたくなる
戻りたくなる
あの道は新しくなる
帰りたくなる
戻りたくなる
過ごした日々は何処にある?
学ぶ意味を今はわからないでしょう
遠い未来夢見る大人の背中
待ちきれないねと語り合えば
心に愛が分かる計りが出来る
いつの日か俺らは大人になれる
いつの日か俺らは大人になれる
泣きじゃくる夜も
笑いあえた今日も
全ては僕の宝物
僕らを染める
夕焼け空を
死ぬまで忘れはしないでしょう
いつの日か俺らは大人になれる
いつだって僕らはあの日のままだ
帰りたくなる
戻りたくなる
あの道は新しくなる
抱きしめたくなる
抱きしめたくなる
歩みを辞めず生きてゆこう
泣きじゃくる夜も
笑いあえた今日も
全ては僕の宝物
帰りたくなる
戻りたくなる
過ごした日々は此処にある
いつだって僕らはあの日のままだ
今日だって僕らはあの日のままだ
『橙』歌詞の意味&楽曲背景
曲のタイトル『橙(だいだい)』は、夕焼けの色。それは、昼(子ども)と夜(大人)のあいだにある、やさしくて切ない”境界の色”です。
さらに、日本語の「だいだい」は「代々」という言葉とも響き合い、時間のつながりや、記憶の受け継がれ方をほのめかしています。
そんな意味が込められているように、この曲は、夕焼けのあたたかさと変わっていく街の姿、自分の内側の気持ちとまわりの世界の変化、過去と今、それらすべてを同時に大切にしようとする楽曲です。
ずっと受け継がれてきた思い出のバトンを、”今日の自分たち”があらためて受け取る。その瞬間に見える色こそが、まさに『橙』なのです。
公式音源の紹介
公開されている公式音源がこちら。
ここからはフレーズごとに歌詞考察をしていきます。
1番:歌詞の意味
1番Aメロの歌詞。
学んだ日々を思い出すでしょう
幼き日に見た夕焼け空を
懐かしいねと語り合えば
現実に愛のある毛布が掛かる
冒頭の「学んだ日々」という言葉は、学校での毎日のことを指すだけでなく、「泣いたり笑ったりした思い出が積み重なった日々」、つまりその人の人生の一部をぎゅっと縮めた形。
そのすぐ後に「幼い日に見た夕焼け空」が出てきて、象徴的な色である”橙(だいだい)色”が登場します。ここで、「学び(=理性)」と「夕焼け(=感情)」という、異なる二つの側面が並べて描かれます。
そして「懐かしいねと語り合えば」という表現が大切です。懐かしさというのは、自分ひとりの中だけにある感情ではなく、誰かと話すことで初めて力を持つ「社会的な感情」として描かれています。ここに、”僕ら”という複数の人を主語とする視点が土台としてあるのです。
さらに「現実に愛のある毛布が掛かる」という部分では、抽象的な言葉である「愛」が、やわらかくてあたたかい「毛布」という、肌で感じられる具体的なものに置き換えられています。
毛布は、寒さや疲れを前提として存在するものであり、「現実の厳しさを消しはしないが、やわらげる」役割を持っているものです。つまりこの曲では、懐かしさをただの「過去への逃避」ではなく、「今の現実に効く温もり」として新しくとらえ直しているのではないでしょうか。
また、「でしょう」という語尾には、断定をやわらげる効果があります。これは聴き手に、自分の記憶や感情を思い出してもらうための”余白”を作ってくれているのだと思います。
このやわらかさが、後に出てくる力強い宣言の言葉との対比を生み、曲全体に呼吸のような抑揚を与えているように感じました。
続く1番Bメロの歌詞。
いつだって僕らはあの日のままだ
いつだって僕らはあの日のままだ
ここで繰り返されるフレーズは、みんなで一緒に歌える「格言(名言のような短い言葉)」としての役割を果たしているように感じました。
たとえば、「いつだって」という言葉は、過去・現在・未来のどの時期にも当てはまる広い時間を指します。「僕ら」は、聞いている人たち全員を含む”みんな”の主語。そして「あの日」は、それぞれが自分にとっての大切な日を自由に思い浮かべることができる、意味が固定されていない「空白の枠」のようなものです。
このようにして、「誰にでも当てはまる普遍性」と「自分だけの思い出に結びつく個人的な意味」の両方が、一つの言葉の中で共存しています。
音楽としては、この部分でコード進行が盛り上がり、言葉がまるで応援の掛け声のように聞こえるようになります。文学的には、過去の思い出をただ「記録」するのではなく、今この瞬間に「思い出を再体験」するよう促す、心に残る短いメッセージになっています。
また、この言葉が「過去にとらわれすぎる危うさ」を持たないのは、「まま」という表現がカギになっているようにも感じました。「まま」は、大事な”中身”は変えずに保ちつつ、その周りの状況や環境が変わっていくことを否定しない、やわらかな響きを持っています。
そしてこの考え方は、後に出てくる「道は新しくなる」という言葉ともつながりそうです。つまり、「大切なものはそのままにしておきながら、外側の世界や自分は変わっていける」という、二つの要素(変わらない核 × 変わっていく外側)を同時に描く準備が、この時点で始まっているのではないでしょうか。
そして1番サビの歌詞。
帰りたくなる
戻りたくなる
あの道は新しくなる
帰りたくなる
戻りたくなる
過ごした日々は何処にある?
このパートでは、動詞が次々と出てくることでテンポが上がり、まるで「体が先に動き出すような衝動」が再現されています。
「帰る」と「戻る」は似ているようで意味が違います。「帰る」は、自分が本来いるべき場所、つまり「心の拠りどころ」や「大切な人のもと」に帰ることを意味します。一方で「戻る」は、以前にいた場所や状態に「物理的に復帰する」ことを表す言葉です。この2つの言葉をあえて並べて使うことで、主人公の思いが「人との関係」や「思い出の場所(通学路など)」の両方に向いていることが感じ取れます。
そして、サビの中心にあるのは、「あの道は新しくなる」という一文です。ここで初めて、「外の世界が変わっていく」という現実がはっきりと示されます。
たとえば、道路が舗装され直されたり、建物が建て替えられたり、街路樹が成長していたりと、日常の中のちょっとした変化が積み重なっていきます。こうした変化によって、かつての風景はもう二度と完全には再現できません。
だからこそ、「過ごした日々は何処にある?」という問いが生まれるのではないでしょうか。この疑問文は、すぐに答えを出すためではなく、曲の後半で答えを見つけていくための”始まり”のような役割を持っています。そして聴いている人が、それぞれの「自分にとっての”どこ”」を探し始めるきっかけにもなるのです。
サビを疑問符で終えるこの作り方は、聴き終わったあとも心が未来へと開かれていくような感覚を残す、大森くんらしい印象的な表現ではないでしょうか。
2番:歌詞の意味
2番Aメロの歌詞。
学ぶ意味を今はわからないでしょう
遠い未来夢見る大人の背中
待ちきれないねと語り合えば
心に愛が分かる計りが出来る
2番では、視線が「今」から「未来」へと移っていきます。
「学ぶ意味がよくわからない今」は、誰もが通る”思春期のモヤモヤした時期”を表す言葉。その「モヤ(霧)」を、「大人の背中」という具体的なイメージで描くことで、聴き手にとって理解しやすい手がかりが与えられています。
「待ちきれないね」という言葉は、一見すると焦っているように思えますが、ここでは「イライラ」ではなく、「ワクワク感が高まっている」ことを意味しているように感じました。この前向きな感情が、その後に登場する「計り(はかり)」の比喩へと自然につながっていきます。
そして「心に愛が分かる計りが出来る」というフレーズは、この曲の中でも特に印象深い名言の一つです。
ここでは、「愛」という目に見えないものを、あたかも測ることができる”量”として描いています。もちろん本当に計りが作れるわけではありません。ここで言いたいのは、「いろんな経験を重ねることで、自分の中に”愛を見分けられる感覚”が育っていく」ということではないでしょうか。
1番に出てきた「毛布」は、相手を思いやる温かさを象徴していましたが、2番の「計り」は「これは本当にやさしさなのか、正しさなのか」を判断するための基準(倫理)を表しています。つまりこの2つは、それぞれ違う役割を持った”人との関わり方の道具”なのではないでしょうか。
このように、ただやさしくするだけでなく、「どうやって正しくやさしくあれるか」を描くことで、感情だけに偏らない、しっかりとした成熟した成長が表現されているのだと思います。
さらに、「出来る」という言葉が使われている点も重要です。これは、誰かから与えられるのではなく、「自分の中から自然に育っていく力」であることを示しています。だからこそこの表現は、単なる”感動する話”ではなく、「自分自身が成長していく物語」として、強く心に残るのかもしれません。
続く2番Bメロの歌詞。
いつの日か俺らは大人になれる
いつの日か俺らは大人になれる
ここでは、主語が「僕ら」から「俺ら」に変わります。
「俺ら」という言い方は、少しラフな表現です。そのぶん、気取らない仲間同士の確かなつながりや信頼が感じられます。親しい間柄だからこそ使える、砕けた一体感のある言葉です。
また、「なれる」という表現は、「もうなった」という達成の意味ではなく、「きっとなれるかもしれない」という”可能性”を含んでいます。これにより、「夢はまだ遠いけれど、そこに向かうことはできる」という、現実的で正直な希望が伝わってきます。
この「なれる」が2回繰り返されることで、1番で出てきた「いつだって」と鏡のように呼応しているのではないでしょうか。
つまり、「いつだって」=どんなときでも変わらない”核”(大切な想い)、「いつの日か」=いつかきっと変わっていく”殻”(未来の姿)という、対になるふたつの時間感覚が描かれ、歌のテーマがより深まっているように感じました。
言い換えれば、この部分は未来に向かって飛び立つジャンプ台のような役割を持っているのだと思います。
1番では、思い出の中にある「ぬくもり(心の足場)」を整え、2番Aメロでは、「判断の軸(心の計器)」を手に入れ、そしてBメロでついに、「跳べる」と自分たちで言えるようになる。
この三段階の流れが、聴いている人の中に、「よし、自分も進めるかもしれない」という静かだけど確かな勇気を育ててくれるのだと思います。
そして2番サビの歌詞。
泣きじゃくる夜も
笑いあえた今日も
全ては僕の宝物
僕らを染める
夕焼け空を
死ぬまで忘れはしないでしょう
ここでは、これまでの経験の価値をまとめるような表現がされています。
「泣く」と「笑う」という、一見対立する感情をあえて同じラインに並べて語っているのがポイントです。これは、「良いことだけが大切なのではなく、泣いたことも笑ったことも含めて、全部が大事だった」と伝えているということ。つまり、どんな結果であれ「ちゃんと生きた」という事実にこそ価値がある、という考え方です。
そしてそれらの経験を「宝物」と呼ぶことで、重たくなりがちな時間の記憶を、子どもらしい純粋さでやさしく包み込むような、日常の詩に変えています。
「僕らを染める/夕焼け空」という表現もとても象徴的です。ここでは、「世界が変わる」のではなく、「自分たちのほうが夕焼けに染まっていく」と言っています。この表現からは、外の景色を通して内面が変化していく、という成長のイメージが浮かんできました。
夕焼けの色である橙(だいだい)色は、心理的にも「安心感」や「親しみ」を感じさせる暖かい色です。そして、昼と夜のあいだの時間を象徴する色でもあり、「子どもから大人へ」の移り変わり=成長のタイミングを表現するのにぴったりだなと感じました。
さらに、「だいだい」という音は、日本語では”代々”=世代を超えて受け継がれるという言葉とも響き合います。これにより、夕焼けが単なる個人の思い出を越えて、「記憶が次の世代へとつながっていく」ような広がりのあるイメージにもなっています。
最後の「忘れはしないでしょう」という表現も見逃せません。ここでは「忘れない」と強く言い切るのではなく、「忘れはしないでしょう」と、”は”という助詞を添えて、やわらかく、でも確かに否定しています。この言い回しは、やさしい口調の中に深い決意が込められていて、聴く人の心に長く残るやさしい約束のように響きます。
そしてブリッジパートが続きます。
いつの日か俺らは大人になれる
いつだって僕らはあの日のままだ
ここでは、「未来に向かう宣言」と「今の気持ちの確信」という、一見すると矛盾しそうな2つの内容が、同じ場面で並べて語られます。
しかし、この並置こそがポイントで、曲が伝えようとしているのは、「変わっていく中にも、変わらずに持ち続けるものがある」という深いメッセージではないでしょうか。変化と持続は対立するものではなく、両立できるものだという哲学的な考えにたどり着いているのだと思いました。
ここで改めて思い出したいのが、曲のタイトルにある色「橙(だいだい)」です。
橙色は、昼(=子ども)と夜(=大人)のあいだにある、夕方の空の色です。この「境目の色」は、「子どもでも大人でもない自分」「過去と未来のあいだに立つ今の自分」を象徴しています。つまりこの曲のテーマである、「どちらかに決めるのではなく、両方を抱きしめて進む」という姿勢が、色によっても支えられているのです。
音楽的には、ここで一瞬、静けさ(間)が訪れるような構成になっています。その静けさによって、言葉の一つひとつに深みが生まれ、内面の声に耳を傾けるような感覚になります。
その余韻のまま、曲はクライマックスであるラスサビへと進んでいくのです。感情の流れを止めずに、むしろより濃く深くしていく、丁寧な構成だなと感じました。
ラスサビ前半の歌詞。
帰りたくなる
戻りたくなる
あの道は新しくなる
抱きしめたくなる
抱きしめたくなる
歩みを辞めず生きてゆこう
1番のサビで出てきた言葉が、ここでふたたび登場します。しかし今回は、それに「抱きしめたくなる」という新しいフレーズが加わります。
この「抱きしめたい」という気持ちは、最初は道(=思い出の場所)に向けられていたものですが、今は「君」や「仲間」、そして自分自身にまで広がっています。つまり、過去の記憶をたどる気持ちは、やがて「今ここにある人との関係を大切にする気持ち」へと変わっていくということではないでしょうか。
そして、「歩みを辞めず生きてゆこう」という一文は、この曲の中で最もはっきりとした前向きな意志の表明です。1番では「過ごした日々は何処にある?」と問いかけて終わっていたのに対し、ここでは「だから、歩き続けよう」と行動で答える形になっています。
この流れは、曲の中での学びの積み重ねを表しているように感じました。
最初は「毛布」で心を温め、次に「計り」で大切なものを見極め、そして最後に「足を前に出す」という能動的な選択にたどり着く。つまり、成長のプロセスそのものが、言葉の順番に込められているのではないでしょうか。
さらに、ここでもう一度「あの道は新しくなる」というフレーズが登場します。
これは、昔のままではいられない「現実の変化」をちゃんと受け止めようとする姿勢を示していそうです。変わってしまった街を否定せず、むしろその変化すら受け入れて大切にしようとするやさしさが感じられました。
そしてラスサビ後半の歌詞。
泣きじゃくる夜も
笑いあえた今日も
全ては僕の宝物
帰りたくなる
戻りたくなる
過ごした日々は此処にある
いつだって僕らはあの日のままだ
今日だって僕らはあの日のままだ
1番のサビで出てきた問いかけ「過ごした日々は何処にある?」。この疑問に対する答えが、このパートでハッキリと示されます。それが「此処にある」という言葉です。
しかし、この「此処(ここ)」は、どこか特定の地名や場所のことではありません。そうではなくて、今の自分たちの関係性・気持ち・行動、そうした「現在のあり方」の中に、過去の思い出はちゃんと生き続けているという意味なのだと思います。
ここで、「帰る」という言葉も大きく意味を変えます。もうこれは「昔の場所に戻ること」ではなくて、過去をどう受け止めて、今をどう生きるかという、心の姿勢の問題になっているのです。
つまり、懐かしさは過去に戻るための鍵ではなく、これから前に進んでいくためのエネルギーになるということ。この考え方がとても重要なのだと思います。
曲全体の構成を見ても、「問い」から始まり、「内面の変化(計りの比喩)」を経て、「意志の表明(歩みを辞めずに生きる)」へ、そして最後に「気づきと発見(此処にある)」へとたどり着く。
このように、まるで人の成長を描いた学びのカーブのような流れが、綺麗に完結しています。特に最後の一文「今日だって僕らはあの日のままだ」は、本当に深く心に響きます。
これは、過去を「そのまま閉じ込めた思い出」として扱っているのではなく、「今日という日、今という時間の中に、あの日の記憶が何度でも書き加えられていく」という逆説的な見方をしているのだと思います。
「今日」も、「明日」も、そのたびに”あの日”が更新され続ける。だからこそこの曲は、聴くたびにその時の「自分」によって、まったく違った意味を持つようになるのです。
そしてその変わり続ける普遍性こそが、大森くんの言葉が長く心に残り続ける理由だと言えるでしょう。
ぜひ歌詞の意味にも注目しながら、この曲『橙』を聴いてみて下さい!
その他ミセスのおすすめ曲
-320x180.jpg)
-320x180.jpg)
-320x180.jpg)
-320x180.jpg)
-320x180.jpg)
今なら無料で音楽聴き放題!
\\いつでも解約OK!//

-1.jpg)



-640x360.jpg)
-640x360.jpg)
』歌詞【意味&考察】ABEMA『今日、好きになりました。初虹編』主題歌(ミセス)-640x360.jpg)
-640x360.jpg)
-640x360.jpg)
-640x360.jpg)